

History of kamagata
先代が語る社史
現社長〈鎌形憲一〉の父で、当社二代目社長にあたる〈鎌形四郎〉が生前に書き記した社史です。
語りべの「私」は四郎自身のことであり、文中の「親父」は、四郎の父(現社長の祖父)になります。

第1話
鎌形建設の前身「鎌形製材所」誕生!
鎌形建設は、私 四郎の親父(=現社長の祖父)が立ち上げた会社で、最初は製材所から始まりました。
親父は小学校3年生の時に大工さんのところに丁稚奉公にいき、薪割りや飯炊きもやっていました。本当に真面目な人間で…こつこつと地道に仕事を積み重ねて22歳の時に棟梁になりました。結婚したのもその22歳の時なんです。その頃から色々な方面に親父の真面目さが伝わり、周りから仕事を頼まれるようになりました。
頼まれた仕事の中に『うちの山の木を使って家を建てて欲しい』という注文がありました。その当時は珍しい事ではなかったので、その注文を受けて親父は丸太を製材工場に持ち込んだのですが、当時の製材工場の人間は気まぐれな人が多く、直ぐには引き受けてくれませんでした。 何度か頼み込んだのですが、色よい返事をもらえなかったので、『じゃあ自分でやろう!』という事で、自分で木を伐採し丸太を山から運び込み自分で製材して、それを使って何とか家を建てさせたのが独立のきっかけだったそうです。 そのうち製材工場として材木を置くようにしたのですが、当時は”山は持っていてもお金はもっていない”人の多かった時代でしたので… だんだんと『うちの山の木を買ってくれないか?』という話がきまして、それで『建築の請負を本格的にやろう』という決心をし、昭和14年に鎌形製材所の誕生となったのです。私はその3年後の昭和17年に誕生するんですが、その当時の親父は朝から晩まで働き詰めで生まれてきた私を初めてみたのは1週間後だったそうです。
頼まれた仕事の中に『うちの山の木を使って家を建てて欲しい』という注文がありました。その当時は珍しい事ではなかったので、その注文を受けて親父は丸太を製材工場に持ち込んだのですが、当時の製材工場の人間は気まぐれな人が多く、直ぐには引き受けてくれませんでした。 何度か頼み込んだのですが、色よい返事をもらえなかったので、『じゃあ自分でやろう!』という事で、自分で木を伐採し丸太を山から運び込み自分で製材して、それを使って何とか家を建てさせたのが独立のきっかけだったそうです。 そのうち製材工場として材木を置くようにしたのですが、当時は”山は持っていてもお金はもっていない”人の多かった時代でしたので… だんだんと『うちの山の木を買ってくれないか?』という話がきまして、それで『建築の請負を本格的にやろう』という決心をし、昭和14年に鎌形製材所の誕生となったのです。私はその3年後の昭和17年に誕生するんですが、その当時の親父は朝から晩まで働き詰めで生まれてきた私を初めてみたのは1週間後だったそうです。



第2話
木造以外の事業を着手‥‥
経営の危機を乗り越えるきっかけ
親父は製材所や木造建築の請負をしていましたので、当然、物心つく頃には私も毎日手伝いをさせられました。朝から晩まで本当にこまねずみのように働いていました。
私には5つ違いの兄がおります。兄も親父の仕事を手伝っていましたので、兄が後を継ぐのが当然と思っていましたが、親父と兄の仲があまり良くない(笑)親父は本当にかたい職人かたぎ、兄は勉強が出来る天才肌。方向性の違いが露わになり、私が小学校2年の頃には「鎌形製材所の跡継ぎは四郎だ!」と決められてしまったんです。
将来の道だけでなく、高校進学の際には「地元の高校へ行け」と言われ、進路もきめられてしまいました。親父によって狭い多古から出られないという寂しさがありました。しかし地元にずっと永くいるもんだから、色々なご縁、深いご縁を頂けました。
高校を卒業してから、私自身は営業を積極的にやり始めました。でもそんな簡単に仕事が頂ける訳じゃない。小さな仕事だったり、親父の信用で話のあった仕事を私が御用聞きに向かうという日々でした。
高校を卒業してから、私自身は営業を積極的にやり始めました。でもそんな簡単に仕事が頂ける訳じゃない。小さな仕事だったり、親父の信用で話のあった仕事を私が御用聞きに向かうという日々でした。
昭和42年の私が25歳になった時、多古町から鉄筋コンクリート2階建公民館の入札業者として指名して頂けたんです。木造以外の仕事は施工した事がありませんでしたので、こんな大きな仕事のお話が、私の所に来た嬉しさで頑張って落札をしたんです。
しかし施工は分からない事だらけで…唯一の救いは兄が大手ゼネコンに在籍していましたので、相談にのってもらい、また、休日は現場を見てもらい、何とか現場を完成させました。しかし素人会社が鉄筋コンクリート造を初めて施工する訳ですから、当然赤字になりました。それが発端で『鎌形は倒産するぞ』と周囲の噂になりました。
親父が積み上げてきた信用や実績を、私一人で全て壊してしまったようで、本当に苦しかった。そんな苦しい状況を見るにみかねて、家の新築を依頼してくれる人がいたんです。当時の金額で1千万円の豪邸でした。しかもその方は契約直後に「鎌形、これ持っていけや…」とポンっと5百万円払ってくれたんです。帰り道は涙で歩けませんでした。家に帰ると親父が「良かったな」って言ってくれて…初めて親父に認められた気がしました。


第3話
運が舞い込む そして『木造の鎌形』と呼ばれ
その後は運が舞い込みましたね。
うちは製材所をやっていましたし、色々な大工さんが出入りしていた事もあり、同業者から造成地域の情報をもらう事が出来たんです。造成されている土地があればその上には住宅が建つ訳ですから…飛び込みで営業したり、つてをたどって紹介して頂いたりで徐々に仕事が増えていきました。その中で一番多くの仕事を施工させて頂いたのは、千葉県住宅供給公社さんでした。供給公社さんのお仕事をさせて頂く前に、都市公社さんで3棟の住宅を施工し、実績ができたので、供給公社さんの木造建築の入札にも参加させて頂けるようになりました。その後は順調に受注させて頂き、棟数を増やす事ができました。
茂原の緑が丘ニュータウンで企画の早い段階から営業していましたので、設計から携わらせて頂き、県内の老舗の建築業者よりも多くの棟数を完成する事ができ、千葉県では「木造の鎌形」と呼ばれるまで成長できたのです。
茂原の緑ケ丘ニュータウンを購入された方が、「非常に良い造りだ!」とほめて頂き、お客様を紹介してくださった事もあるんです。人のご縁、地元のご縁に本当に助けられました。


第4話
社長就任!
経営者の立場を意識した出来事
私が29歳の時に親父が亡くなりました。急な事だったので悲しみよりも不安の方が大きかった事を覚えています。しかし会社は続けなければいけませんので、私が社長に就任しました。経営など素人の私は本当に不安な毎日でした。そんな時、亡くなった親父に世話になったからと、入社していろいろと私の面倒を見てくれた人がいました。十分に給料も払えない会社なのに、私を一生懸命一人前の社長に育ててくれて…後に、専務として本当に会社に尽くしてくれた人なんです。
その専務が「とにかく社長は外に出て営業をしてほしい。事務所は私が守るので、何でも思いっきりやってほしい!」と言ってくれて、私は営業に専念できるゆとりが出来たのです。
ゆとりができると、気の緩みも出てきまして(笑)、お客さんとの付き合いで夜遅くまでお酒を飲む事が多くなり、出社が9時、10時に出社する事が頻繁になりました。そんなある晩、専務から自宅に呼ばれ一緒に酒を飲みました。その時専務から「いくら酒を飲んでも良いから、朝9時、10時に出社するなんて事はやめなさい!」ときつく怒られました。慢心していた私は心を入れ替え次の日から一番早く出社し会社の鍵を開けて社員を待つようにしました。
その専務は私が66才の時に亡くなったのです。親父より一緒にいた時間が長かったですから、二人目の親父を見送った気持ちでした。今でも専務には本当に感謝しています。



第5話
木造の仕事を極める!
重要文化財の復興作業を行う
その後、専務の言葉をきっかけに私自身が経営者としての自覚を持って地道に営業活動を行って数年が経過した頃、当社にとっては木造の仕事を極める事ができたと言っても過言ではない仕事をやらせて頂いたんです。
それは歴史的建築物である、旧学習院初等科正堂の移築工事でした。旧学習院初等科正堂とは、明治三十二年に建設された正堂が、昭和十二年に東京都四谷から成田の遠山尋堂小学校の講堂として移築された建物です。昭和四十八年に遠山小学校の新講堂建築の為、この講堂が栄町の風土記の丘へ移築する事が決まりました。
風土記の丘に移築する時には国から重要文化財として指定されました。 そうなると簡単な話ではありません。明治時代の建物を復元させる高度な技術が必要となります。非常に繊細な仕事である為、競争入札でありましたが、予定価格に達する業者がおりませんでした。各業者が尻込みするような難しい仕事なら鎌形でやってみようと思い、なんとか落札させたのです。
しかし、各業者が尻込みするような工事ですから、移設作業も簡単には進みません。まずは歴史的な建物の情報収集から始めました。京都、名古屋、高山の歴史的建築物を何度も何度も見に行き文献を読み、博物館にも行きました。それと一番重要なのは腕の良い大工さんの確保です。たまたま知り合いのつてで、手先のとても器用で歴史的建築物を手掛けた事のある大工さんを確保し、お願いする事ができました。完成させるにはこれが一番大きかったです。
完成までは1年半もの時間がかかりました。多くの時間はかかりましたが、とても良い仕事をさせて頂きました。無事に完成出来た事、腕の良い大工さんと知り合えた事など本当に運が良かったです。
工事を無事完成させた事の他に嬉しい事がありました。風土記の丘が開場して間もなく、私の小学校の恩師が多人数の先生方と風土記の丘に視察に来られたそうです。
旧学習院講堂を視察している時、この移築工事は鎌形建設が施工した事が分かり、皆に自慢したそうです。その夜に先生から電話を頂いて、先生が自分の事のように皆に自慢した事を聞いて本当に嬉しくなりました。


第6話
京葉銀行さんとのご縁をきっかけに
自社の営業体制が整った
実はこの場所に本社を建設する前は同じ多古町内でも、本町という場所に住居兼本社を構えていました。親父が、ある工事を請負った時に赤字を出してしまって…その赤字整理の為に、住居兼事務所の土地と建物を売らなければならなくなったのです。
その時に土地と建物を買ってくれたのが京葉銀行さんで、その場所に京葉銀行多古支店が建てられたのです。
その後、私が社長就任してからの苦しい時期も色々と助けてくれたり、住宅を建てるお客様の融資の話にも親身になって頂くなど、お付き合いを続けさせて頂きました。
平成2年には、京葉銀行さんの富里支店を建築する事ができたのです。銀行さんの支店を任されるまでに成長したのだなと思ったら感慨も一入でした。その富里支店建築中に京葉銀行の方が「鎌形建設はよくやってるよ」と近隣の地主さんにお話ししてくれた事がきっかけで仕事に結びついたりという事もありました。
私が社長になってからは京葉銀行さん一筋です。良い人材も紹介してもらえています。今いる民間担当の営業部長も京葉銀行さんからの紹介です。それまでは私が社長兼営業部長だったのですが(笑)、その営業部長が来てくれてからは営業の人材を積極的に採用・教育し、営業の幅が大きく広がりました。彼の入社によってマンション事業であるユーミーマンション事業が大きく発展し、更にカナダの輸入住宅であるセルコホーム事業を導入するきっかけを見つけてくれたのです。
京葉銀行さんとの最初のきっかけは、私の住んでいた所の売買でしたが、人の紹介から事業拡大まで人と人との繋がりを築かせて頂いた事は、弊社にとってとても大きな財産です。
私が社長になってからは京葉銀行さん一筋です。良い人材も紹介してもらえています。今いる民間担当の営業部長も京葉銀行さんからの紹介です。それまでは私が社長兼営業部長だったのですが(笑)、その営業部長が来てくれてからは営業の人材を積極的に採用・教育し、営業の幅が大きく広がりました。彼の入社によってマンション事業であるユーミーマンション事業が大きく発展し、更にカナダの輸入住宅であるセルコホーム事業を導入するきっかけを見つけてくれたのです。
京葉銀行さんとの最初のきっかけは、私の住んでいた所の売買でしたが、人の紹介から事業拡大まで人と人との繋がりを築かせて頂いた事は、弊社にとってとても大きな財産です。


第7話
コスト改革!ユーミーマンション事業を導入
ユーミーマンションを導入したのが平成6年でした。
それまでの当社は公共工事の仕事が9割以上でした。良い物を造っている自身はあったのですが、民間建築での価格競争にどうしても勝てない。今後は「民間建築を伸ばさなければいけない!」と考えていた時なので、何とかコストを抑える事を考えていたのです。
そのおりに前出の営業部長がユーミーマンションを探してきたのです。当時の我が社では、マンションを安く建てる技術もノウハウもありませんでした。その技術を提供してもらい指導してもらう為にFC(フランチャイズ)に加盟する事にしました。
当時この地域には、プレファブ造とか木造の集合住宅はありましたが、鉄筋コンクリート造のマンションは少なかったのです。あったとしても家賃がかなり高かったりして…その点ユーミーマンションは建築の段階からコストを抑えていますから、当然家賃も安くできるのです。
同程度の家賃であれば、木造アパートより鉄筋コンクリート造のマンションを選びますよね?そのような条件もあり、ユーミーマンションの平均入居率は、全国で96%とすばらしい数字を誇っています。更に当社が手掛けた物件は、平成22年4月現在では入居率98%となっておりお客様にも大変喜んで頂いております。 ユーミーマンション事業を導入したおかげで、コストを抑えるノウハウが会社に残りました。そして何より良かったのは、地元にオーナーさんが数多く出来たという事です。当社でマンションを建築して頂いたオーナーさんが新しいお客様を紹介して下さったり、マンションの入居者の方が当社を気にいって頂いて、住宅を新築して下さったりと、かけがえのない人との繋がりを呼んできてくれているのです。
当時この地域には、プレファブ造とか木造の集合住宅はありましたが、鉄筋コンクリート造のマンションは少なかったのです。あったとしても家賃がかなり高かったりして…その点ユーミーマンションは建築の段階からコストを抑えていますから、当然家賃も安くできるのです。
同程度の家賃であれば、木造アパートより鉄筋コンクリート造のマンションを選びますよね?そのような条件もあり、ユーミーマンションの平均入居率は、全国で96%とすばらしい数字を誇っています。更に当社が手掛けた物件は、平成22年4月現在では入居率98%となっておりお客様にも大変喜んで頂いております。 ユーミーマンション事業を導入したおかげで、コストを抑えるノウハウが会社に残りました。そして何より良かったのは、地元にオーナーさんが数多く出来たという事です。当社でマンションを建築して頂いたオーナーさんが新しいお客様を紹介して下さったり、マンションの入居者の方が当社を気にいって頂いて、住宅を新築して下さったりと、かけがえのない人との繋がりを呼んできてくれているのです。



第8話
新たな出会い!
輸入住宅セルコホームの導入
輸入住宅であるセルコホーム導入のきっかけは、営業部長から出た話なのです。その部長がある日曜日の朝に自宅のテレビで「成長企業」という番組を見ていたら、セルコホームが紹介されていたそうです。番組が終わると営業部長から電話があり、「ツーバイフォー(2×4)より地震に強いツーバイシックス(2×6)住宅で、それもカナダの輸入住宅だから、少し変わっていて面白そうだ」と言われ、すぐにテレビ局に電話をして連絡先を尋ねて、セルコホームの本部に連絡を取りました。
セルコホームの本部は仙台にありました。電話をしたところ、是非展示場を見てほしいと言われたので、テレビ放映の2日後には仙台まで行って展示場を2つ見てきました。初冬の仙台なので外は寒いが、家の中は全然寒くない。外の音も聞こえず遮音性にも優れていました。ああ…これは良い!と思い早速パートナーシップに加盟する事にしたのです。
機能的にも防音、耐震と本当に優れていました。セルコホームの場合は、標準がツーバイシックス(2×6)です。ツーバイフォー(2×4)が標準の他社では耐震性能をUPさせるとツーバイシックスになるのですが、セルコホームはツーバイシックスが標準ですから最初から高品質な商品が提供できる訳です。今ではツーバイシックス住宅施工の経験豊富さが当社にとって大きな差別化となっています。
お客様もそれを分かってくださり、安心してセルコホームを選んで下さっている方が増えているのは大変光栄です。
セルコホームは平成10年から営業体制を整えています。平成21年の秋には高グレード仕様の展示場を成田でオープンしました。
多くのお客様にお越し頂き、従来の住宅には無いグレード感や本物の質感を味わって頂いております。まだ体感しておられない方にも是非お越し頂きたい自慢の仕様です。


第9話
クレドの導入
クレド(credo)とはラテン語で、日本語に訳すと「信条」という意味になります。企業の信条や行動指針を簡潔に明文化したものです。既に有名ホテルや百貨店、メーカーなどで導入されていますが、建設業界で導入している企業は少ないようです。
親父の代から私の代になり、製材所、在来住宅建築、公共工事、重要文化財の移築、土地造成、道路工事、RCマンション建築、賃貸管理、倉庫建築、住宅リフォーム、輸入住宅建築、高級在来住宅など様々な事業を行ってまいりました。
地元に根ざして、お客様や社員という財産に恵まれここまで成長する事ができました。社員数も70名を超えるまでになりました。社員の勤続年数も長くなり、自分の子供を鎌形建設で働かせたいと子供さんを託してくれる方もおられます。
地元の人で成り立っている鎌形建設なのです。本社も移転せずに地元にこだわって頑張ってやってきました。地元の人に住む家を提供し、働く場を提供する。これは継続し、大きく発展させていかなければならないと思っています。
地元に根ざして、お客様や社員という財産に恵まれここまで成長する事ができました。社員数も70名を超えるまでになりました。社員の勤続年数も長くなり、自分の子供を鎌形建設で働かせたいと子供さんを託してくれる方もおられます。
地元の人で成り立っている鎌形建設なのです。本社も移転せずに地元にこだわって頑張ってやってきました。地元の人に住む家を提供し、働く場を提供する。これは継続し、大きく発展させていかなければならないと思っています。
[私たちのクレド]
私たちは、出逢った全ての人々に感動を与え、
喜びを分かちあえる会社でありたい。


第10話
私の夢!多古町をブランド化したい
クレドの導入や浸透活動を通じて社内の雰囲気が明るくなりました。今後は、お客様に対して、より積極的に、より明るく働きかけてくれる人材になれるように社員一人一人に対して期待をしています。実は、私の夢のひとつに「地元である多古町をブランド化したい」というものがあります。米百俵という話が有名になりましたが、これは長岡藩の話です。しかし、多古町にも同じような話があるのです。
明治35年に多古町の先輩方が「土地に良い田んぼを!」という事でこの近辺の田んぼを耕地整理しました。これは石川県についで全国で2番目の早さで当時画期的な試みだったのです。この耕地整理事業の成功を褒章し農林大臣より金一封が授与されました。この報奨金を基金として明治40年に多古町立乙種農学校が設立されたのです。それが現在の多古高等学校の前身です。多古の先輩方は、色々苦労して多古の風土に合うお米を探し、探し当てたのが現在の多古米なのです。
多古の田んぼは土質が軟らかく、お米作りには苦労するのですが、その分日本でも上位、千葉県ではいすみ米と並び美味しいと評価されていて有名なのです。
多古米のネームバリューはまだ低いですが、今、日本は農業がブームになりつつあります。自前で色々作るという事が見直され、家庭菜園をする人も増えています。多古米や作物を作りやすい環境と建物をうまく結び付けて多古町をブランド化できれば良いなと思っています。
当社は、農家の方を通じて畑を貸して頂く事が可能なのです。今お借りしている畑はすぐ近くに舗装された町の駐車場と水洗トイレが完備されています。こんなに恵まれた環境ばかりではありませんが、今後農業をやりたい方や家庭菜園をしたい方には、是非多古へ移住して頂きたいと願います。近隣地域の移住であっても、多古の畑を貸し出せるような企画も今後は考えたいと思っています。
我々が持っている商品や知識や技術や人脈を、多古のブランド化に貢献できるようにしたいですね。


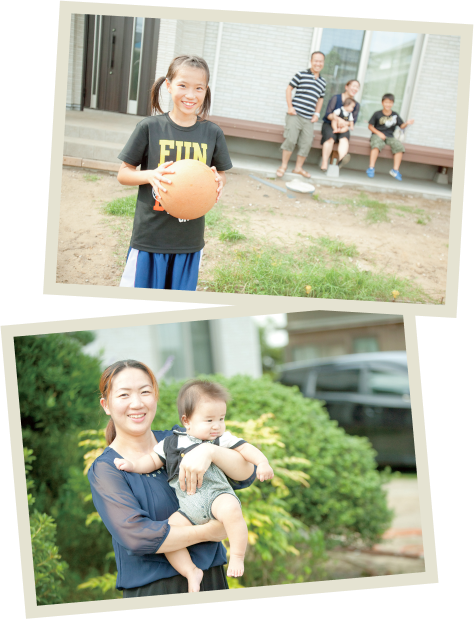
第11話
多古町を拠点として
今後も『住の総合事業』にこだわりたい
当社は、親父の代に大工の棟梁を経て製材所からスタートした会社ですが、今では、在来住宅建築、公共工事、重要文化財の移築、土地造成、RCマンション建築、道路工事、倉庫建築、住宅リフォーム、輸入住宅建築、賃貸管理など総合的に「住」にまつわる事業を行っています。早いもので、20年前当社で家を建てて下さったお客様の子供が今では当社の社員として活躍してくれています。
また、地元の農家の方や地主様には、新たに家賃収入という生活基盤を提供させて頂き、生活の安定や向上に貢献させて頂けている事も嬉しく思っています。今後も当社が発展し続ける事で、地元の皆様に更に良い居住空間を提供できるようになり、それを通じてお客様になってくださった方だけでなく、地域社会にも貢献していければ良いなと思っています。
本社のあります多古町でも、東日本大震災の被害は発生しました。瓦が落ちたり、道路や駐車場が陥没したりしました。何人ものお客様から修繕のご依頼を頂戴しました。普段からお世話になっている分、なるべく早く皆様のお役に立てればと思っていますが、すぐ壊れてしまいそうな緊急度の高い方を優先させていただきました。ご容赦くださいませ。
震災を含め、日本全体でも様々な問題が発生しております。建設業に関連するところで言えば、財政赤字に伴う公共事業の減少、人口問題では少子高齢化、地域間を含めた格差の問題、それらに伴った空き家問題等です。どの問題も大きく、一企業がどうする事も出来ませんが地域の皆さんと共に解決策を見出しながら活動していく、それが一番の地域貢献であり、そんな会社でありたいと思っております。
当社では数年前から多古町でイベントを行っております。多古町島地区の方にいつもご協力を頂き感謝しております。今では1回のイベントで300名以上もお越し頂けるまでになりました。もっと手を加えて地元の交流の場にし、更には地元以外の方々がこちらの地域に移住して頂ける何かしらのきっかけを当社が作れるようになれればと願ってやみません。
人と人との繋がりを大切にファンを多くする事が鎌形建設の向上力となり、多古町をブランド化させる事ができるよう、尚一層の努力をしてまいりますので、皆様のご指導を宜しくお願い申し上げます。

